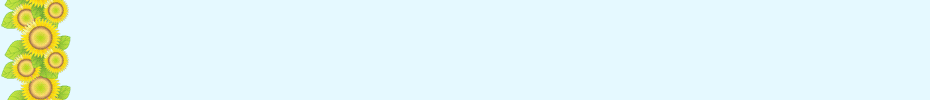子供の時、僕たちの間で流行っていたのは、ビー玉を集める事だった。
キラキラと光って太陽にすかして見ると、違う世界がその中にあるようで、みんなで夢中になって集めていたっけ。
僕はその中でもとびっきりに奇麗で、誰もが羨ましがるような奴を手に入れた。
でも、その一番の宝物は何処かへ消えてしまった。
いくら探してみてもみつからない。その時の僕は無くしてしまった事が悔しすぎて、夜眠る事だって中々出来なかった。
でも、もう二度と僕の元には戻らないだろうと諦めたビー玉は、ある朝目覚めると枕元に置かれていた。
鞄や机の中それと家の庭、自分で思いつく限りのありとあらゆる場所を探しても見つからなかった宝物が戻ってきたのが不思議で、子供だった僕はそれを奇跡だと思った。
そんな話を彼女にしたら「想う気持ちが強ければ、その想いは何かに届くんだね」と笑顔で答えてくれた。
真相は、僕のズボンのポケットに入ったままのビー玉を、母が洗濯の時にみつけてくれて枕元に置いたのだが、それは言わぬが花って奴だろう。奇跡は奇跡のまま存在した方が良いし、彼女の笑顔が膨れっ面になるのはちょっといただけないから。
雨に濡れたスーツをハンガーにかけてから、久しく吸わなかったタバコに火をつけた。
スーツの湿った匂いと、タバコの煙の匂いが妙に体にまとわりついて嫌な感じだ。
これはクリーニングに出さなければいけないだろう。普段着ない黒いスーツを最近は何度も着ている。
留守番電話のランプが点滅しているが、メッセージを聞くのも億劫で、僕は殆ど吸うことなく灰になったタバコを灰皿に押し付けてから。
濡れた髪を乾かさずベットに潜り込み、深い眠りが訪れるのを待つことにした。
僕はあの日からずっと、一番大切な物が欠けているこの部屋で、書くことだけのために存在している。
それは例えるなら自分の中にある井戸の水をくみ上げて水瓶に移すようなものだ。
きっとこの作業はいずれ終わりを迎えるだろう。
以前は枯れる事無く次から次へと書くべき事が自分の中のどこかから溢れていたのに、今ではその水は一滴も湧き上がってこない。
だから僕は決めている。自分の中の井戸が最後の一滴までも使い果たされた時どうするかを。
書けなくなる事が辛いのではなく、大切な物を失ったまま書くべきものも見つけられず生きていくのは辛すぎるから。
出来る事ならあの時のビー玉のように、自分の元に戻ってきて欲しいと願っている。
『想う気持ちが強ければ、その想いは何かに届く』本当にそうであってくれればいいのに。
でも、それはどう考えても無理な事なのだ。
それこそ、奇跡でも起こらなければ。
昼休みに、近所の小学校の校庭で子供たちが駆けずり回って、嬌声を上げているのが、ここに引越ししてから僕の目覚まし代わりになっている、こんな時間に起きても支障の無いのが自由業の気楽さって奴だ。
どうも夢見が悪くてそれがどんな夢だったのかも思い出せない。寝汗をかいているからあまり良い夢ではないのだろう、もっとも、今の僕の状況でよい夢が見られるとも思えないのだが。
少しふらつく頭をスッキリさせる為に、シャワーでも浴びようかとバスルームに向かった。
そして僕は、鏡に映る自分の姿にあっけにとられた。
これは一体なんだろう、いや何であるかは判っている。でも、本来自分にはあるべき物ではないし、過去においても在ったという記憶も無い。
ひょっとしたら、単に寝ぼけているだけでこんな物は無いのかもしれない、もしくはまだ夢の中に居るのだろうか?今朝になって僕にしっぽが生えているのだから。
とりあえずこのままでは不便なので、ジーパンを一本しっぽが出るように穴を開けた。
シャワーを浴びてようやく頭がすっきりした後も、僕にはしっぽが生えたままだったからだ。
長さは50センチくらいで、黒い短毛種の猫のような感じで。こいつが、僕の意思と関係なく左右に揺れたりピンと立ったりしている。
行動もまるで好奇心旺盛な猫その物のようだ。この殺風景で物の少ない部屋を観察している。
僕はしっぽが生えたというより、生き物が家に住み着いたような気がしていたし、あまり考えすぎるのも面倒なので、この奇妙な体験をすんなりと受け入れてしまう事にした。
もう一つ理由をあげるとするなら、一人でこの部屋に居るのが嫌だったからかもしれない
しっぽとの共同生活で、一番の不便は寝返りをうてなくなったことだ。
反対側に寝返りをうとうとするとどうしても邪魔になる。
そういえば、猫好きな彼女がこんな事を言っていたっけ。
「うちの猫が布団に潜ってくるとなんか、寝返りうてないんだよね寝てるの起こしちゃいそうだし、それで布団から出てかれちゃうのもなんか寂しくって」
僕の場合は、自分の体の一部だから、布団から勝手に出てくってことはないが、別の生き物と一緒に居るって感じがするので、なんとなくその言葉に共感めいたものがあったりするから、僕もしっぽに対して遠慮がちになったりする。
外出のときは、少しすその長い薄手のコートを羽織って出かければ、特に問題もない、もっとも僕が出かけるのなんて、近所のコンビニか、人気のない昼間の図書館くらいだ。
冷蔵庫の中を覗いてみると、ミネラルウオーターくらいしか入ってない事に気付いた僕は、財布をコートのポケットに入れて、久しぶりに出掛けることにした。
男の一人暮らしとは言え、全く冷蔵庫に中身が無いのでは話しにならないので、思ったより大量の荷物になってしまった。
スーパーの袋を両手に持って、マンションまで戻ろうとした途中で、しっぽがしきりとモゾモゾする。
そして、しっぽに引っ張られるような感じがしてそちらを振り返ってみると、そこにはケーキ屋があった。
確か、ここのケーキはモンブランが最高らしく、彼女は僕の原稿料が入るとお祝いだと言って、買ってきては喜んでいたっけ。
しっぽもどうやらここのケーキに惹かれているようだ。
物を食べれるわけでもないし、言葉を発してる訳でもないのになんとなくそんな感じがした僕は、荷物が沢山あるにも関らず「モンブランを2つ下さい」と言って更に荷物を一つ増やした。
部屋に戻ると食材を冷蔵庫に詰めてから、ケーキを自分の分は手づかみで食べ、しっぽの分は書き損じの原稿用紙の上に乗せて自分の後ろへ置いた。
しかもティーパックではあるものの、紅茶はしっぽの分を入れている。
そんな自分自身に対してクスクスと笑ってしまった。無精物の僕にしては、破格の特別扱いってやつをしっぽに対してしているのだから。
きっと、はたから見れば奇妙な光景で、僕がおかしくなってしまったんじゃないかって思われるだろうが、やっぱりしっぽはこのケーキに凄く喜んでいるみたいで、あっちへパタパタこっちでパタパタと、ひっきりなしに動いている。
これだけ喜んでいるのなら、自分の奇妙な行動も別に良いんじゃないかと思えてくる。
僕は特に甘い物は苦手でもないが好きと言う程でもない、それでも今日食べたケーキはとても美味しかった。久しぶりに食べ物を口にしたと言う実感が湧く。
最近の僕は砂をかんでいるような味気ない食べ方しかしていなかったからだ。
クリームのついた手を子供のように舐めてから。
「お前も自分で、食べられたら良かったのにな」
しっぽに向かって話し掛けると、しっぽはそうだねと答えるように、先っぽの方だけをクイっと動かして後は大人しくなった。
しっぽの分のケーキは、そのまま一時間くらい置いておいたが、このままにしてても仕方ないので冷蔵庫にしまってから「後で僕が食べてやるよ」と少し意地悪そうな声でしっぽに向かって言うと、パシッと僕の腰の辺りにしっぽがぶつかった。
そんな行動がいかにも悔しそうだったのが楽しくて、僕は思わずゲラゲラと笑ってしまった。
このしっぽとの奇妙な共同生活らしきものは、思ったよりも快適だった。
元来面倒見の良いほうではない僕にとって、食事を与えたり世話をきちんと焼かないといけない生き物と一緒に生活するのは、かなり難しいことだろうと思う。
でも、しっぽは勝手に僕に生えているし、適度になんらかのアクションを起こして僕を和ませてくれるのと同時に、元々体の一部として存在していたのではないだろうかと、錯覚してしまう程に僕になじんでいる。
それに、しっぽを見ていると少しだけ心の空白が埋められて行くのだ。
僕はこの日、いくつか抱えていた締め切りに向けて、ずっとパソコンの画面とニラメッコをして過ごしていた。
さすがに疲れて一つ伸びをしてから仕事の手を休め、コーヒーでも入れようかと立ち上がると電話が鳴った。
そのままにしておけば留守番電話に切り替わるのでほおっておくと、お決まりの機械のメッセージが流れる。
「おい俺だ、居るんだろういいかげん電話に出ろよ、近くまで来てるんだ」
電話の声は学生時代からの友人鈴木のものだった。
僕は本当に仕方なくといった感じで電話に出た。
いれたばかりのコーヒーを二つ、テーブルの上に置いた。
鈴木はすまないなという仕草をして、砂糖とミルクを適当に入れてかき回すが、一口飲んで眉間に皺を寄せた。
彼はコーヒーを普段はブラックで飲むのだ。
多分手持ち無沙汰で、とりあえず何かしなければ場が持たないからしてしまった動作だったのだろう。
僕は自分の分には砂糖とミルクを入れた。
「なぁ、お前大丈夫か?」
「何が?」
僕の問い返しに鈴木は髪の毛をかき回した。
これは彼が困った時にするクセみたいなもので、何について大丈夫かと聞かれたか皆目見当もつかない僕の方が困ってしまう。
「相変らず表情が見えないよな、お前」
そういえば、学生時代に「鉄仮面」なんてありがたくないあだ名を僕につけてくれたのは彼だった。
「みんな心配してるんだぞ、電話にも出ないし姿だってちっとも現さないし」
「別に仕事はちゃんとしてるよ、この前の原稿だってちゃんと届いてるだろ」
三日前に彼のもとにFAXで原稿は送ってあるはずだ。
「それは、ちゃんと届いてるけど。お前は仕事に逃げてるんだよ」と、鈴木は歯切れの悪い声でぼそぼそと言い、その後意を決したようにはっきりとした声で言った。
「俺が心配してるのは仕事の事じゃないし、それに葵も心配するぞ、残されたお前がそんなんじゃ」
その時僕は、かなり冷たい視線を彼に向けたんだと思う。鈴木は僕を見て、しまったという表情を浮かべた。
僕の頭の中は真っ白になって思考が停止されていた。いやそうではない、本当はこの言葉を自分の中で遮断したかった。
そして、わざわざ他人の口から思い知らされたくなかったのだ。
彼女がもうこの世に居ないと言う事を。
葵は僕の一番の理解者であり、僕と結婚するはずだった人だ。
彼女がこの世から居なくなってしまったのは結婚式当日だった。
式場まで向かう車がトラックの居眠り運転事故に巻き込まれたからで。
幸せの絶頂に居た僕は、式場に中々現れない彼女の事を、こんな時に遅刻だなんてよっぽど前日眠れなかったんだろうと呑気に思っていた。
そして、事故の連絡を受けたその瞬間、僕のタキシードは喪服になり、彼女のウェディングドレスは、死に装束となっのだ。
未だに荷物の片付いていないこの部屋は、彼女と一緒に暮らすつもりで越してきた場所だった。
葵は大学時代に出会った人で、タマタマサークルで書いたミニコミ誌の僕の雑文を気に入ったと言って、人付き合いの悪い僕になんだかんだとまとわりつき、気付くと側に居るのが当たり前な存在になっていた。
彼女と居る時間が長くなり、書くと言う事が彼女の存在のおかげで呼吸をするかのように自然と出来るようになっていき、今までの人生とは違った色で周りの景色が見える。
葵が居ることにしっくりと馴染んでいく間に、僕にも何人かの友達付き合いをする仲間が出来ていったが、それは葵がいなければ築けなかった人脈だったと思う。
「ヒロちゃんは、損してるんだよね、中身は色んな物で溢れてるのに、それを表現するの苦手でさ、その分文字で表現してるんだろうね」
「そんなもんかな?」
葵はちょっと考える仕草をして、いい事を思いついたといった風に言った。
「しっぽでもあったら判りやすいのにね」
「それって、犬のしっぽみたいに?」
僕がそう聞き返すと、彼女は笑って。
「そう、でも今は私が居るから大丈夫、鉄仮面のあだ名も返上だって」
得意そうに言う彼女がとても愛しかった。
「すまん、俺はデリカシーがどうにも無いらしいな」
僕が黙り込んでしまった事で、鈴木は益々居心地が悪くなってきたらしい。
でも、僕にはそんな彼を気遣う余裕もないし、彼にも僕が何を考えているかなんて判るはずもなく、鈴木はしばらくすると帰っていったようだ。
ここに最後に来た日とはうって変わって酷く天気の良い日だった。
「ごめんな、なかなかここに来る勇気が出なくって」
葵の墓の前に立ち、僕は彼女の好きだった向日葵の花束を供えた。黄色い太陽が似合う花は、彼女そのもののようだ。
花嫁のブーケにも使う事にしていたので見ていると、少し切ない気分なった。
あれから葵と一緒に居た頃の事を思い出したり、彼女が居ない事を自分の中で受け入れられるように努力をして、最終的に僕はここにやって来た。
しっぽはしゅんとしおれている、僕はなんとなく思っていた。このしっぽが自分以外には見えないのではないのかと。
そして、実際は存在すらしていないのではないかと疑ってもいた。
今はまだ、しっぽは僕の眼には見えているのだが、それは僕が作り出した幻想で、本当は何も無い空間に向かって話し掛けていただけなのかもしれない。
モンブランが好きで、猫を追い出せないのも、僕の中の井戸を満たしてくれるのも葵なのだ。
彼女の事を失った悲しみが大きすぎて、その現実を受け入れる事がどうしても出来なくて、僕は無意識のうちに何かにすがりつきたくなったのだろうか?
出来ればそうではなく、本当に葵が僕の元にやって来てくれたんだと思いたい。
感情表現下手な僕の変わりに、彼女がその感情を引き受けてくれようとして。
「葵。まだ側に居てくれるかい?」
しっぽは、先っぽの方を少しだけ動かしてみせた。
まるで「まだ居てもいいの?」と遠慮がちに聞いているようだ。
ここに来ても、僕はまだ葵が自分の元に居ないのだと言う事を、完全に受け入れることが出来なかった。
幻想でも何でも良い。どんな形であれ、お互いが一緒に居る事が必要なのだ。
しっぽを見つめていると、僕はとても満たされた気持ちになり。
そして、それとは別に心の片隅に不安もあった。
どんな形であるかは知らないけど、いずれ訪れるであろう別れに対して、自分達が耐えられるのかを。
本当はこんな事ではいけないのだろう、そう判っていてもこの小さな幸せを手放す事は出来なかった。僕たちはあまりにも悲しみを知ってしまったから。
お互いの居ない寂しい世界で生きて行くと言う事を。
僕は祈る。
もし、この奇跡を起こした誰かがいるとしたならば、どうかこのままで居させてください。
僕たちが、互いにやすらげる時がくるまでと……。
|
|
|
|